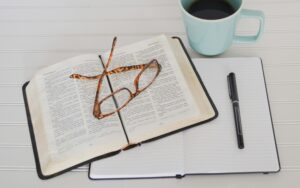はじめに
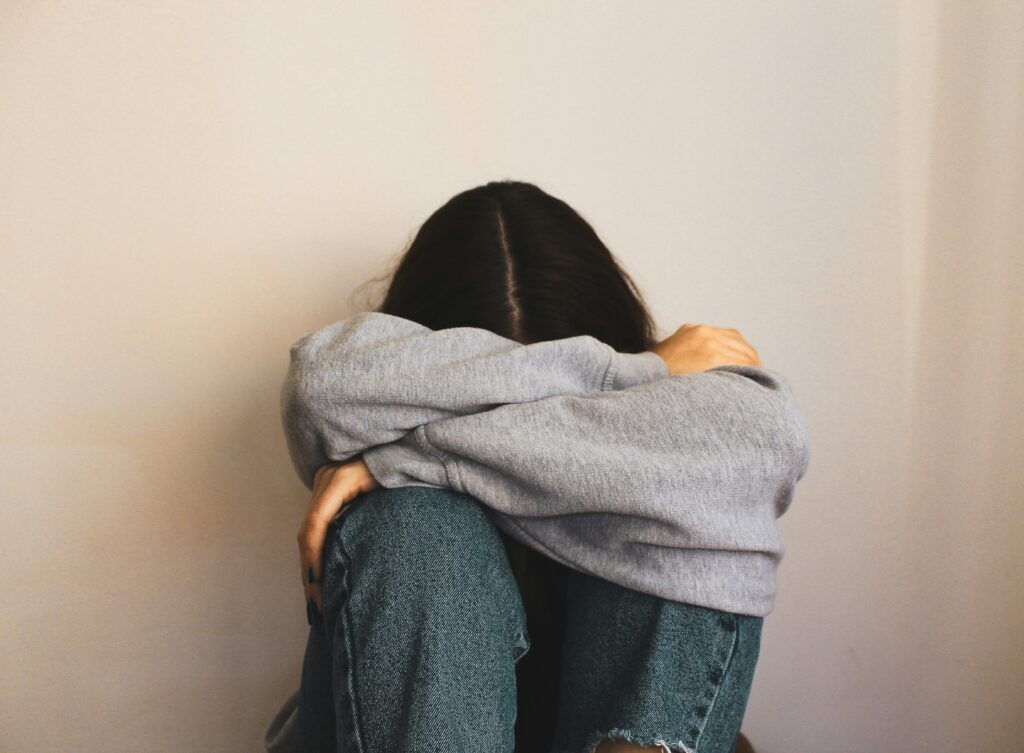
「海外赴任が決まったけど、妻として本当に行くべきか…」「もし行って後悔したらどうしよう…」
そんな不安を抱えている方は多いでしょう。
実際に駐在をきっかけに夫婦関係が悪化し、帰国後に離婚に至るケースは少なくありません。
海外赴任中の離婚にまではならずとも、海外赴任中に入った亀裂が埋まらず、関係が悪い中関係が継続しているという話も聞くことがあります。
この記事では、駐在妻のリアルな体験談と離婚率の現実をデータで示しつつ、後悔しないために今できる準備と対策を詳しく解説します。
あなたとパートナーが安心して海外生活を送るためのヒントをお届けします。
【結論】海外駐在で離婚率が高い理由

海外駐在が離婚のきっかけになる背景には、明確な理由があります。
たとえば日本国内の単身赴任家庭の離婚率は、同居家庭の約2倍と言われていますが、海外赴任はさらにメンタル負担が大きくなることが多いのです。
代表的な理由
- 慣れない海外生活で心身のバランスを崩す
- 配偶者間の役割が極端に分担され、不満が溜まる
- 異国での孤独感や孤立感が想像以上に大きい
- 不倫や浮気のリスクが高まる
- 子育てや教育問題で夫婦の意見がすれ違う
国によっては妻が働けない場合も多く、「誰とも話さずに1日が終わる」状況が続けば、夫婦間の小さなズレも大きな溝になっていきます。
実際に多い駐在きっかけの離婚理由TOP5
1. メンタルストレスと孤立感
海外駐在妻の多くは、現地での言語の壁、生活習慣の違い、文化の違いに適応するだけで相当なストレスを抱えます。
特に専業主婦になる場合、社会との接点がほとんどなくなり、“自分だけ取り残されたような感覚”に陥る人も。

子育てがある場合は現地の学校制度や言語サポートの壁も大きな負担です。
加えて、夫は仕事が忙しく家にいないことが多く、相談相手がいない孤立状態が長期化します。
LINEやSNSで友人とつながれる時代でも、時差や話題のズレが孤独感を強めてしまうことがあります。
2. 価値観のズレが深刻化
駐在生活は日本での共働き時代とは役割が一変します。
日本では共働きで家事も折半、家計も折半だったところから、働くのもお金を稼げるのも夫のみという状況になります。
しかも、望んでその形になったわけではなく、妻側は家庭のために、苦渋の決断をしたということもあるでしょう。
そこから、「妻は家で支えるもの」「夫は仕事に専念」という形が突然強制されていき、キャリアを手放した妻が自己肯定感を失っていき、メンタルが不安定になっていくということが、起こりやすいのです。
夫側は「過去はどうだったとしても働いて稼いでいるのは自分だけだったのに」
妻側は「夫がそうやって働けているのは、私が仕事を諦めてこうやって一緒に赴任したからなのに」
キャリアを断念したストレスがこうして夫婦の衝突につながっていきます。
3. 駐在妻コミュニティのストレス
表面的には心強いはずの駐在妻ネットワークも、実際は噂話や上下関係で疲弊する声が絶えません。
気が合わない人間関係を避けると孤立、付き合いすぎるとストレス…。
バランスを取るのが難しいのです。
離れられる関係性であればいいのですが、お子さんの学校や夫側の会社の付き合いなど、どうしても逃げられない人間関係もあります。
日本では、人間関係に困ったことが無かったような人でも、こうして狭い人間関係に悩まされることもあるのです。
4. 子なし・単身赴任の選択が裏目に
ここまでは海外赴任の帯同した場合の話を中心にしてきましたが、夫婦が物理的に離れる単身赴任も、時間が経つほど心の距離が離れます。
時差や赴任後の忙しさも相まって、日本に残って子育てや仕事をしている妻側の話を聞く時間がなくなり、「自分一人で子育て/仕事を頑張っている感覚」や「頑張っていることを誰も気づいていない感覚」に陥りやすいです。
実際に、、時間差で海外赴任に帯同した家族では、現地に行ってから上の不満がなくなり、関係性が改善したという話を聞いたことがあります。
また、子どもがいない場合は、時間ができたこと、孤独感が倍増したことから、浮気や不倫などのきっかけにもなりやすいのもつらいですが現状です。
逆にきつい環境に無理に帯同しても妻がメンタル不調に陥れば同じ結果を招きます。
5. 浮気・不倫のリスク
駐在先でのパーティー文化や異性との付き合いが日本よりカジュアルな国も多く、浮気が現実化しやすいのも事実です。
夫だけでなく、孤独な妻が現地で気持ちが揺れるケースもあり、男女問わず監視が効かない環境が離婚率を上げているという可能性も示唆されています。
【体験談】リアルな声を知り、妻が駐在後に直面する課題を知りましょう
Yahoo!知恵袋や発言小町には、駐在妻の切実な声が溢れています。
「夫が海外赴任するけど、正直ついていくのが怖い。現地で子育てと孤立に耐えられる自信がありません。」
「駐在妻同士の集まりが辛かった。噂やマウンティングが多く、誰も信用できなくなった。」
このような実体験を知っておくだけでも、事前の心構えが変わります。
駐在の離婚を避けるためにできるのは、家族での徹底的な話し合いです

海外赴任が決まった時点で、メリットだけでなくデメリットも家族で徹底的に共有しましょう。
「とりあえず行ってみる」では後戻りができないこともあります。
子育て・教育方針、現地での仕事の有無、サポート体制を事前にリサーチし、役割分担を明確にするのがポイントです。
もし可能であれば一度事前に下見渡航をしてみたうえで下記点を話し合ってみましょう
(難しい場合は夫にチェックリストを持たせて下見してきてもらう。SNSの声をさがすのもありです)
メンタルケアを前提にする
駐在妻のメンタルダウンを防ぐには、現地でのカウンセリングやオンラインカウンセリングを選択肢に入れましょう。
日本ではまだまだ病気の人が使うものというイメージがあるカウンセリングですが、海外では体調をよく保つために活用されています。
孤立感が強まる前に小さな不安を相談できる場を用意しておくことが大切です。
気軽に話せる相手がいるだけで心の負担は大きく変わります。
もし少しでも不安な気持ちが大きくなったときに「誰に話を聞いてもらうか」「その状態をどうやって夫に伝えるか」準備しておくことが大切です。
Cotreeなどオンラインでも使えるカウンセリングが今はたくさんあります。
環境づくりと居場所の確保
現地で孤立しないために、駐在妻コミュニティだけに依存しないのも大事です。
趣味やボランティア、語学学校など外の居場所を複数つくり、関係がこじれたときの逃げ道を確保しておきましょう。
どうしても関係性が少ないと旦那さんや駐在妻コミュニティに頼りがちになります。
よく行くスーパーの店員さんやマッサージのお店の人など、深い関係ではない人でも大丈夫です。
少しでも依存先の数を増やせると、どこかでうまく行かなかったときも他に頼ることができます。
時には現地人のお友達が助けになってくれることもあるでしょう。
選択肢を夫婦で共有し、どちらの立場も尊重し合うことが何よりの予防策です。
離婚を選ぶなら?海外での手続きと帰国後の流れ
もし海外在住中に離婚を決断する夫婦も少なくありません。
しかし、国際離婚は国ごとに手続きが異なり、思わぬトラブルが起きやすいです。
海外での離婚手続きの基本
- 駐在国の法律を確認する
駐在国によって離婚が認められる条件や必要書類が違います。 - 日本大使館に相談する
国によっては大使館で離婚届を受理できる場合がありますが、必ずしも全ての国で対応しているわけではありません。 - 日本での効力を確認する
駐在国で離婚が成立しても、日本で戸籍に反映させるには追加手続きが必要な場合があります。専門家への相談が安心です。
必要な準備と書類
- 婚姻証明書(翻訳が必要)
- 離婚協議書(合意内容を明文化)
- 子どもの親権に関する合意書
- 両国の法律に合った手続きサポートを依頼
帯同の場合、離婚後はビザが使えなくなることもあるので、必ず大使館に相談しましょう。
できれば下記の日本での手続きを推奨します。
帰国後の流れと準備ポイント
帰国後に離婚を決める夫婦も多いです。
理由は「子どもの学校を切りの良いタイミングで転校させたい」「現地での手続きよりも日本の方がスムーズ」などです。
スムーズに進めるコツ
- 駐在中から弁護士に相談しておく
- 財産分与・親権について夫婦で取り決める
- 住む場所や子どもの転校先をリサーチ
- 仕事復帰や収入計画を考えておく
無計画な帰国後離婚は、経済的に苦しくなるリスクが高いので、具体的なライフプランを描いておきましょう。
まとめ 〜幸せに海外生活を送るために大切なこと〜
海外駐在は人生の大きなチャンスでもありますが、夫婦にとっては大きな試練でもあります。だからこそ、
- 夫婦で何度も話し合い、価値観を共有する
- 妻が孤立しない環境を複数つくる
- 必要なら第三者に頼る勇気を持つ
これが何より大切です。
パートナーと「一緒に乗り越える」姿勢が、後悔しない選択につながります。この記事を読んだあなたが、心から安心できる駐在生活を送れることを願っています。
FAQ
Q1. 単身赴任か帯同か、どちらが良い?
A. 一概にどちらが正解とは言えませんが、夫婦で話し合い、どちらの方が妻の孤立やストレスを減らせるかを基準に考えましょう。
単身赴任は心理的距離が生まれやすいので注意しましょう。
Q2. 帰国後すぐに離婚できる?
A. 可能ですが、戸籍や住民票の手続きが必要です。特に子どもの転校・引っ越しのタイミングを考慮して計画しましょう。
Q3. 離婚するか迷っているが、誰に相談すればいい?
A. 駐在国の大使館、オンライン法律相談、日本の弁護士、駐在経験者コミュニティなど、複数の選択肢があります。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談を。
Q4. 駐在中に仕事復帰できる?
A. 国によっては就労ビザが不要なオンラインワークが増えています。
現地の規制を調べ、副業やスキルアップを検討しましょう。
Q5. 離婚後の生活が不安です。何を準備すべき?
A. 帰国後の住まい・仕事・子どもの学校・生活費の見通しを具体化しましょう。
自治体の支援窓口やカウンセラーも活用してください。