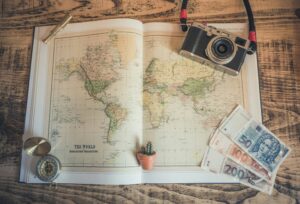1. インド駐在で日本食材が大事な理由

「インドって住んでいる日本人もたくさんいるし、何でもそろうんじゃないの?」
私もそう思っていました。でも、現地での食材探しは想像以上に大変です。
宗教上の理由や物流事情で、お肉・だし・調味料など、買えそうで買えない物が多いのが現実。
また日本では安く買える調味料もインドだと5倍以上の値段がする、なんてことも、、、
しかも、せっかく買っても「なんか違う、、、」とちょっとした味の違いが大きなストレスになります。
だからこそ、赴任前に「何をどれだけ持って行くか」を考えるだけで、
インド生活の快適さが変わると断言します。
別の記事でインドで手に入るもの、についても解説しますので、ご参考になさってください。

2. 【体験談】私が実際に持って行った日本食材と理由
ここでは、私が実際にインド駐在で「持って行ってよかった!」と思った日本食材を、
カテゴリー別に紹介します。
🔹 調味料編
✅ 和風だし(かつお・昆布・煮干し)
インドでは、和風だしは手に入りません。手に入っても高価だったり業務用サイズしかなかったり。
味噌汁や煮物に必須なおだしですが、お腹を壊した時にも、必ずほしくなる味です。
✅ お味噌
意外と地域のこだわりが出るお味噌。インドでは1種類くらいしかなかったので、自分の地元のお味噌を持っていきました。
お腹を壊して善玉菌が流れた後は、日本の発酵食品が効きます。天然の薬としてもおすすめです。
✅ 鶏ガラスープの素・コンソメ
洋食系スープや炒め物で大活躍。ベジタリアンが多いことと、だしの文化がないことから、現地のスーパーでは手に入りません。
✅ ごま油・ラー油・マヨネーズ
これも「現地品で代替できる」と思って持って行かなかったら、現地の味が全然違い後悔しました。
ごま油は「セサミオイル」としてインドにも存在するのですが、日本のごま油は焙煎ごま油。インドのものは生のごま油。
日本の香ばしいごま油を想像して食べると、生臭くてびっくりすると思います。
✅ カレールウ
インドなのに、日本のルウが一番恋しくなります(笑)。
✅ めんつゆ
後述する醤油は手に入るのですが、めんつゆは持参しました!
🔹 レトルト・保存食品編
✅ インスタント味噌汁
疲れた日の救世主。乾燥わかめ・乾燥ネギ付きがおすすめ。
✅ レトルトご飯
現地の米で合わない時や、忙しい時に便利。
✅ ふりかけ・お茶漬けの素・炊き込みご飯の素
味変で気分が変わります。お子さんがいるとお米のアレンジが効くのが重要と貴重なママさんからのご意見ももらいました!
✅ おかゆ、にゅうめん
なんだかおばあちゃんが好きそうな食事!と思われるかもしれませんが、侮ることなかれ。
インドで急激な腹痛に襲われた後、これしか食べられないことがあります。
✅ おさかな缶詰
インドのお魚は淡水魚中心であまり味がしません。鯛などもありますが、とても高いです。
私はイワシ、サバの缶詰は大量に買っていきました。味の調整がしやすいように水煮がおすすめです。
🔹 主食・乾物編
✅ お米
インドでも日本米に近いものはありますが、買い物に行けるくらい生活に慣れるまでには時間がかかります。
少量だけでも持って行くのがおすすめ。
最初は水の不安もあると思うので、無洗米を持参しました!
✅ カップラーメン
時々無性に食べたくなる味。。。!
インドだと一つ500円~1000円くらいすることもあるので絶対に持参がおすすめ
✅ 海の乾物、山の乾物(ふるさと納税)
マストではないのですが、インドに行く前のふるさと納税で乾物を購入しました。日本の冷蔵庫はふるさと納税いっぱいだったので持ちこめてむしろ助かりました。
お手軽な乾物セットはこちら
| 【ふるさと納税】海・山・里の乾物おまかせセット 価格:5,500円(税込、送料無料) (2025/7/2時点) |
✅ 乾燥豆腐
現地で豆腐も打っているのですが、人パック3,400円くらいしてたかかったので持参しました。
乾燥豆腐や高野豆腐が人気です。
🔹 お菓子・嗜好品編
✅ おせんべい・干し梅
小腹満たしに最適。意外とインドで買えません。
✅ お茶(麦茶・緑茶)
飲み慣れたお茶があるだけで安心感が違います。
私は水で溶けるお茶と大好きな玄米茶を持参しました。
ウーロン茶と麦茶人気が周りだと高かったです。
3. 現地で買えるもの・買えないもの最新事情
デリー・グルガオンの日本食材スーパー
代表例:
- ICHIBA(グルガオン):日本人御用達のSouth point mall内に。もちろん割高ですが、大体そろう
- 大和屋(デリー・グルガオン):昔からある日本食材専門店。調味料は割高だけど緊急時に助かる。お惣菜もある
- INAマーケット:アジア野菜が手に入りやすい。たまに栗とか見かける🌰
- Amazon.in:乾物系は意外とインドのAmazonでも買える
代替品と注意点
- 鶏肉はローカルマーケットや日本食材店でも比較的安価で新鮮なものが買える。レバーや砂肝も購入可能。
- 牛肉・豚肉は宗教上ハードルが高く、ほぼ買えない地域も多い。
- 豚肉は日本食スーパーで割高ながら購入可能。牛は時折水牛を見かける
- 一時帰国でまとめ買いする人が多いが、保冷バッグ・税関での工夫が必須
- 醤油はキッコーマンのSoysauseが購入可能。私は持っていきませんでした。
4. 食材の保存方法・運び方【船便・航空便】
船便と航空便の使い分け
日本食材をまとめて送るときは、
船便と航空便、スーツケースをうまく使い分けるのがポイントです。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 船便 | 大量に送れる・安い | 到着まで1〜3ヶ月かかる |
| 航空便 | 早い・急ぎの物に便利 | 重量制限が厳しい・高額 |
私も最初は船便を多用しましたが、「すぐに欲しい物だけ航空便にする」が正解でした。
冷蔵品はスーツケースで持ち込む人が大多数です。
保冷バッグの使い方
冷凍肉や干物を一時帰国で持ち帰る人は必須!
保冷剤+保冷バッグで10時間程度のフライトなら十分持ちます。
✅ ポイント
- 梱包にドライアイスを使う場合は申告必須
- 発泡スチロール、段ボールもうまく活用する
- 空港税関で開けられる可能性あり → 取り出しやすい位置に
- ジップロックで小分けにすると便利
- 保冷剤は溶けても漏れないジェルタイプが安心
税関トラブルを防ぐコツ
実際に私も何度か冷や汗をかきました…。
食材を持ち込むときは👇
✅ 肉・魚は申告ルールを必ず確認する
✅ 税関で開けられやすいので、パッケージをきれいに
✅ 禁止物は持ち込まない!宗教的にNGなものは特に注意
✅ (地味に大事)堂々と通過する!
5. 【便利】楽天で買えるおすすめ日本食材まとめ
駐在準備で一番便利なのが楽天まとめ買い。
私も実際に使いましたが、
まとめてカートに入れておいて、一気に発送が楽です!
一時帰国の際にまとめて持ち帰るようにインドから注文たくさんしている方も多数見かけました笑
🔹 私が買って便利だった物
- 【和風だし】久原のあごだし、茅乃舎だし
- 【鶏ガラ・コンソメ】味の素シリーズ
- 【カレールウ】バーモントカレー、ジャワカレー
- 【レトルト】お手軽パスタソース
- 【レトルト】クックドゥ中華料理の素
- 【ふりかけ】丸美屋シリーズ
- 【保冷バッグ】コールマンの大型バッグ
- 【保冷剤】ロゴスのソフトタイプ
- 番外編:火鍋のもと
6. 【体験談】持っていったけど不要だった物
たくさん買っていったけど、意外といらなかった?というものも多数。
🚫 持って行ったけど不要だったもの
- パスタ:日本のパスタの8割くらいの完成度のものは売っている(特にペンネ)
- トマトピューレ:パックジュースサイズで確か40円くらいだった。
- 大量のお米: 現地にも日本米があり、そんなに味に困らなかった。
7. 番外編:食料が無くなった時、足りなかったときの選択肢
ここまで文章を読んでみて、「こんなにたくさん持ち込めないよ!」という方もいるかもしれません。
駐在中の方に人気なのが買い物も兼ねて周辺国に旅行に行くことです。
特にマレーシア、シンガポール、タイ、ベトナムなどに日本食の買い出し+リフレッシュに行く方も多いです。
下記で紹介していますので、ご覧ください。
まとめ
本日はインド駐在食材おすすめリストをお届けしてきました。
持ち込みリストのイメージは湧いたでしょうか?
これをもとに、自分が食べ物で譲れないものなどを考え、準備を成功させましょう!
インドの食べ物以外の持ち物リストはこちらにまとめています

参考にしたい、生活費の目安はこちらから


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49dfbbbf.15dcded2.49dfbbc0.17ea39da/?me_id=1332653&item_id=10012831&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnipponselect%2Fcabinet%2Fitem%2Fs61%2Fs61590001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)